ヨガの資格を取得して指導を始めてから、心の穏やかさや自分を大切にする生き方を伝えたいと思うようになりました。
ヨガの哲学を通じて、誠実で整った生活を目指す姿に、僕自身も強く惹かれています。
でも正直に言うと、清く正しく生きるという理想を、完全に実践するのは簡単なことではありません。
そんなとき、ヨガの本場であるインドを思い浮かべると、ふと違和感が生まれることがあります。
インドには、数学や科学に強い才能、急成長する経済、温かくて人懐っこい人々といった魅力的なイメージがあります。
一方で、貧富の差や不衛生な環境、さらには詐欺やひったくりといったネガティブな話も耳にします。
特に、ヨガやヒンドゥー教の聖地として知られるガンジス川が不衛生だという話を聞くと、ヨガの純粋さや精神性と結びつけにくいような感覚になります。
僕はまだインドを訪れたことがありませんが、いつか行ってみたいという思いはずっとあります。
だからこそ、こうしたイメージのギャップが、どこから来るのか気になるのです。
ヨガの哲学とインドの現実は、どう繋がっているのか――。
今回はこの違和感について、ヨガを指導する一人として、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
この違和感を紐解くことで、インドの本当の魅力や、ヨガの本質をより深く理解できたら嬉しいです。
ヨガ哲学が教えてくれること

ヨガは単なる運動ではなく、心と身体の調和を大切にする生き方だと、僕は考えています。
指導者として、ヨガ・スートラの中にある八支則をお伝えする中で、ヤマ(禁戒)やニヤマ(勧戒)といった教えを通じて、誠実さや優しさ、そして自己成長の大切さを共有してきました。
たとえば、サティヤ(真実)は「正直に生きること」、アヒムサ(非暴力)は「自分や他人を傷つけないこと」を意味します。
このような教えは、生活のリズムを整え、心の静けさを育んでくれるものです。
僕自身、ヨガの哲学に強く共感しており、レッスンを通じてその清らかさや高潔さを大切にしているつもりです。
クラスの中で、呼吸法やアーサナ(ポーズ)を行う時間は、自分自身と向き合い、心と身体を結びつける大切なひとときです。
生徒さんがヨガを通じて自分を見つめ直す姿を見ると、指導者として大きな喜びを感じます。
とはいえ、どれだけ理想を語っていても、自分自身が完璧でいられるわけではないことも実感しております。
時には欲望に流されたり、忙しさに気を取られたりすることもあります。
それでも、ヨガの教えは、より良い自分に戻るための道しるべとなってくれるのです。
ただ、そのようなヨガの純粋さが、本場インドという国に抱くイメージと少しズレているように感じる瞬間があります。
ヨガの聖地であるインドにまだ訪れたことのない僕にとって、そのギャップはどこからくるものなのか——一度、考えてみたいと思いました。
インドへのイメージとその背景

インドに対して僕たちが抱くイメージは、メディアやSNSを通じて形成されたものが多いのではないかと思います。
スピリチュアルな国という印象がある一方で、「街中はゴミだらけ」「物乞いが多い」「電車の中でもお金をせがまれる」といった体験談を目にすることも少なくありません。
「ヨガの聖地なのに、なぜ街が整っていないのだろう」「人々がヨガ哲学を実践しているなら、もっと穏やかで清潔な国なのでは?」そんな疑問が浮かんでしまうのです。
たとえば、ガンジス川はヨガやヒンドゥー教の聖なる川として知られていますが、汚染が深刻で「茶色い川」というイメージが強いです。
インド料理を食べると「お腹を壊すかも」なんて話や、詐欺やひったくり、客引きのイメージも、旅行の注意点としてよく耳にします。
また、時間を守らないという印象も強く、約束の時間に遅れたり、スケジュールが曖昧だったりする話は、大らかな性格の表れなのかもしれませんが、日本人の感覚とは少し異なる気がします。
しかし、すべてのインドがそんなイメージ通りではないようです。
リシュケシュ、ヨガの聖地として知られるこの場所は、動画で見る限り本当に魅力的です。
ガンジス川の上流に位置するリシュケシュでは、川の水がみなさんが思うような茶色い川ではなく、驚くほど綺麗だそうです。
ヨガの聖地らしく、客引きのような行為も他の地域に比べて少ないと聞きます。
この静かでスピリチュアルな環境に、いつか身を置いてみたいと思います。
このギャップをどう理解したら良いのかを考えていたとき、インドの文化や歴史に目を向けてみると、少しずつ腑に落ちるようになってきました。
インドは多くの民族と宗教が混在する国です。
ヨガが誕生したのはヒンドゥー文化の中ですが、現代のインドでは、ヒンドゥー教徒、イスラム教徒、キリスト教徒などが共に暮らしており、信仰や習慣、考え方は地域によって大きく異なっています。
また、カースト制度の影響も根強く残っており、生まれによって人生の選択肢が制限されてしまうこともあります。
このような社会構造の中で、すべての人がヨガ哲学の理想を実践しているとは限らない、と思いました。
加えて、インドは極端な貧困と急速な発展が混在する国でもあります。
IT産業が急成長する一方で、いまだに教育や衛生環境が整っていない地域も数多くあります。
そのような現実を抱えながら、たとえヨガの教えが身近にあったとしても、日々の生活に追われ、哲学的な実践まで手が回らない人々も多いのではないでしょうか。
つまり、ヨガ=インド人全員が実践しているものではなく、むしろ、そういった現実の中で生まれ、必要とされてきたからこそ、ヨガ哲学が今も大切にされているのではないか。
そんなふうに思えるようになりました。
ヨガは“今を生き抜くための知恵”

ヨガは決して、特別な人だけが実践するものではありません。
むしろ、混沌とした社会や不安定な日常の中で、自分自身を見失わずに生きるための知恵なのだと、僕は思います。
インドという国もまた、矛盾や混沌を抱えたまま、さまざまな問題と共に日々を生きています。
貧富の差や不衛生な環境、時間を守らないゆるやかな生活リズム、カオスな雰囲気——こうした現実があるからこそ、ヨガという知恵が生まれ、今も必要とされているのかもしれません。
けれども、そのカオスに心を奪われる人もいます。
色鮮やかな市場、熱気あふれるお祭り、深い精神性。
一度ハマると、インドの魅力にどっぷり浸かってしまう。
特に、インドにヨガを学びに行った指導者の方々からは、「インドは本当に素晴らしい! 現地のエネルギーとヨガの精神性が心に響く」と熱く語られることが多いです。
リシュケシュを訪れた指導者の話では、ガンジス川の上流の清らかな水辺でヨガをすると、心が洗われるような感覚があるそうです。
客引きが少なく、静かな環境でヨガに集中できるこの場所は、ヨガの聖地として特別な存在だと聞きます。
こうした話を聞くと、いつかインドを訪れ、チャイを飲みながらその空気感を味わってみたいと強く思います。
現代の日本でも、ストレスや不安、孤独を抱える方がたくさんいらっしゃいます。
そんな時代だからこそ、呼吸を整えること、自分の身体を丁寧に扱うこと、感情に振り回されないこと、こうしたヨガの実践は、誰にとっても意味のあるものになるのではないでしょうか。
ヨガを指導する中で、生徒さんがアーサナや呼吸法を通じて少しずつ心の平穏を見つけていく姿を見ると、ヨガの力が現実の生活にも役立つことを実感します。
インドの混沌は、ヨガ哲学の調和と対立するものではなく、むしろそれを生み出す土壌なのかもしれません。
リシュケシュのような場所では、混沌の中にあっても心の静けさを見出せることを、ヨガが教えてくれます。
理想通りに生きることは簡単ではありません。
けれども、自分の中の誠実さや思いやりに立ち返ることは、誰にでもできることです。
ヨガ哲学は、その人の本来の姿に戻る手段として、現代人の心を支えてくれているのだと、私は思います。
まとめ
私が抱いていたインドへの違和感は、偏見や誤解による部分も大きいかもしれません。
詐欺や不衛生は、どの国にもある課題です。
インドをヨガの聖地として大切に思い、その多様性や奥深さに目を向けることで、ヨガの本質にもっと近づける気がします。
いつかリシュケシュを訪れ、ガンジス川のほとりでヨガを体験するのが楽しみです。
ちなみに参考にした動画はこちらです。2人ともめちゃくちゃおもしろい動画を撮影しているのでぜひ見てみてください!





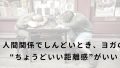

コメント